|
|
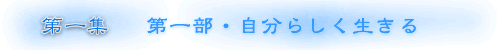 |
主婦
|
平成6年10月22日 |
| 倉坪 芳子さん |
「何事にも信念を持ち ふるさと守りたい」 |
毎月一回、仲間と一緒に土手町をデモしている。「核燃と原発に反対する女たちのデモ」を始めて8年、この十月でそのデモが百回目を迎える。
「子供たちに汚れた故郷を残したくないはんで」とおっとりとした津軽弁で話すのは倉坪芳子さん。津軽生まれの津軽育ち、三人の子のお母さんだ。「雨の日も雪の日も休まずに百回もよく頑張ったなアって思う。もうやめようかと思ったこともあったけどやっぱりこれはジョッパリというか女の意地かな」。柔和な笑顔の中にシンの強さが見える。 |
仲間は女ばかり十人。年齢も出身地も仕事もさまざまだ。手には「かくねんまいね」とパッチワークしたかわいいピンクの横断幕を持つ。最初は恥ずかしくて、知り合いに会わないでほしいと思いながら歩いたという。
何故デモを?「核燃料サイクルへの反対の声があることを町のみんなに知ってほしかったんです。何か意思表示がしたくて。子供たちにも自分の生き方を示したかったんです。後で後悔したくないですから」。最初はけげんな目で眺めていた町の人も今ではおなじみとなり「あんたたちよく頑張るの」と手を振ってくれるという。
七年前には「核燃はイヤ」の小さな声をまとめたいと全国に声を掛け、集めたカンパ二百七十万円を使い、地元紙二紙と全国紙の県版に「かくねんまいね!」の意見広告を出したこともある。人生のパートナーである夫君はなんて? 「意見広告を出すって言った時はおまえ大丈夫なのかと心配していましたが、今ではガンバレって言ってくれます。二十二日の百回目のデモにはいっしょに歩くみたいですよ」とにっこり。
「故郷津軽にとことんこだわりたい」と芳子さんは三年前に津軽三味線を習い始めた。そして二日に岩木町で開かれた「津軽三味線フェスティバル」に初参加し、四百人で「あどはだりパート1」を演奏した。「気分そう快。ねぷたの時みたいに津軽の血が騒ぎました。久しぶりのワクワクドキドキ」と結構ちゃかし。
そして芳子さんがもうひとつこだわるのがリンゴだ。春から秋にかけて毎日リンゴ園にアルバイトに行っている。花摘み、実すぐり、袋掛け、袋はぎ、葉取り、収穫と気の遠くなるような手作業をこなす。
「りんごをこんなに手を掛けて育てるなんて知りませんでした。農家の人の気持ちや痛みがほんの少し分かったような気がします」。これからも故郷津軽にこだわっていきたいという芳子さん。観音様のような笑顔とじょっぱり精神で農作業に三味線、そして核燃まいねのデモとけっぱっていくことだろう。
| |
|
|
|
| 「森のイスキア」を主宰する |
平成6年11月5日掲載 |
| 佐藤 初女さん |
「心を込めた手料理で 悩める人を慰める」 |
憩いの家「森のイスキア」は三方を森に囲まれ、岩木山の懐に抱かれるように建っている。ここを主宰するのが佐藤初女さん。
「ここはだれでも気軽に来てくれていいんですよ。自然の中で自分と向き合えば、本当の自分の気持ちが見えてきます」。初女さんは七十三歳、愛らしい笑顔のおばあちゃん。そばにいるだけで肩から力が抜けて、なんだか優しい自分に戻れる気がする。 そんな初女さんを慕って「森のイスキア」には二年間で全国から五百人が訪れた。ある人は悩みを聞いてほしくて。またある人は初女さんの笑顔に会いたくて。
ここに来た人はみんな「実家に帰ってきたようだ」とくつろぐ。そんな初女さんの生活をフィルムに収めたいと、東京のドキュメンタリー映画監督龍村仁さんが申し出た。 |
映画のカメラは津軽の四季とそこで暮らす初女さんの日常を追う。初女さんは草も花も人もみんな同じ生命を持つ仲間だと考えて暮らしている。フキノトウを摘み、梅干しを漬け、味噌を作るという何気ない初女さんの生活に日本人の知恵を発見したと龍村監督は話す。
初女さんは以前から弘前市桔梗野の自宅を安らぎの家「弘前イスキア」と名付けて、悩みを抱えて苦しむ人の話に耳を傾け、援助するというボランティア活動をしてきた。初女さんのところにはあちらこちらのカウンセリングを受けても解決できず、どうしようもなくなった人が話を聞いてほしくてやって来た。
初女さんは訪れる人をいつでも優しく迎える。死にたいと訴える人もいる。だが初女さんはこうしなさいとアドバイスしたりはしないという。ただその人のために漬物やみそ汁、季節の材料を使ったおいしい手料理をこしらえる。
取材で訪れた日、東京から映画の撮影隊が来ていた。「キクとクルミのあえ物を作りましょう」と初女さんは八歳の孫紀子ちゃんと一緒に擦り鉢でクルミを擦りはじめた。二人の姿を映画のカメラがゆっくりと追う。初女さんは「めんどくさい」という言葉は嫌いだという。「めんどくさいからこれ位でいい」という言葉を聞くと悲しくなる。「今の人はすり鉢で擦るなんてめんどうだって思うかしらね。でもこうやって丁寧にすればクルミの命やすりこぎの木の命がそのままおいしさになって人を元気づけてくれるような気がするでしょう」
「どうせ年取ってしまったんだからなんて言う人がいるけれど、年寄りの果たす役割は大きいんですよ。おばあちゃんでなければ出来ないことを孫の世代に伝えていかないとね」。取材が終わったころには、夕闇が下りていた。「一緒に夕飯を食べていきなさい」といなりずし、きのこのみそ汁、ナスの漬物をごちそうになった。あたたかいみそ汁が身体の中にしみ渡った。
仕事に追われ、自分を見失いそうになる自分の姿に気が付いた。初女さんの笑顔には「目くじら立てて、がむしゃらになる必要なんてないのよ」。そんなメッセージが伝わってきた気がした。
初女さんが主演するドキュメンタリー映画「地球交響曲・第二番」は来春封切りになる。
| |
|
|
|
| 劇団「弘演」創設者のひとり |
平成6年11月19日掲載 |
| 秋本 博子さん |
「ズシリ35年の重み 演劇人生まっしぐら」 |
「あっと言う間でしたね。
夫の作間とふたり劇団を作ろうと弘前に帰ってきたのがついこの間のことのようです。結婚し、子を産み、育てながら好きなことをしてきたんですから幸せですね」。
秋本博子さん、劇団「弘演」の俳優であり、演出家であり、創設者の一人でもある。底抜けに明るい笑顔が印象的な女性だ。博子さんが経営する喫茶「ブラジル」にはコーヒーと演劇好きが集まる。気のいい喫茶店のママというのが博子さんの実生活での役柄。開店して三十五年という年月はそのまま劇団「弘演」の歴史と重なる。 |
生き生きしてますね?「若い劇団員たちと接しているから落ち着く暇ないんですよ。いつもあがいているから若く見えるのかな」。夫であり「弘演」の束ね役でもあった作間雄二さんを亡くしてからの二十年、子供二人を育てながら「弘演」のかなめとして頑張ってきた。
博子さんは俳優を志し、高校卒業後、東京の劇団「文化座」の研究生になっていた。そして「文化座」で俳優として活躍していた作間雄二さんと出会い、二十一歳で結婚。
東京生まれの雄二さんの夢は地方で劇団を作り、地域に根ざした演劇活動をすることだった。「そのころは何かするなら東京にいかなくては駄目だとみんなが思っていた時代でした。地方で頑張りたいという夫の言葉に私も目からうろこが落ちました。作間は津軽弁が大好きでした。美しい言葉だって。それで私の故郷弘前に二人で帰ってきたんです」。
喫茶店を経営しながら同志を募り、昭和三十九年市民会館で「弘演」の旗上げ公演を行った。雄二さんが演出し、博子さんと小学生だった二人の女の子も同じ舞台に立ったこともある。公演前は毎晩十時過ぎまで稽古が続く。二人の子供は練習場の片すみで丸くなって寝ていた。「創立してからずっと赤字、赤字できました。楽な生活ではなかったけれど家族四人の暮らしは幸せでした」。
それから九年後、博子さんと二人の子を残して雄二さんは亡くなる。「生活のことより、子供のことより、劇団をどうやっていくかが何よりも心配でした」と博子さん。「夫が命を掛けて作った劇団をつぶせないと思いました。作間の代わりにはなれないけれど、メンバーと一緒に頑張らなくてはと思いましたね」。
それから二十年の月日が流れた。二十七日には「弘演」の創立三十一年、五十作目の公演が行われる。演出は博子さんが担当し、長女のしのぶさんが女優として舞台に立つ。「今大事にしたいなって思うのは、普通の人が一生懸命生きる姿。今度の公演『恋歌が聞こえる』では何でもない普通の人をしっかり描きたいって思っています」。
母親の姿を見て育った二人の娘さんもまた演劇の道を歩く。「弘演」を愛した両親の気持ちは二人の子供に伝わって、今大きく実ろうとしている。
| |
|
|
|
| 酒・肴処「西海岸」のおかみ |
平成6年12月10日掲載 |
| 森山 美枝子さん |
「不遇の時代バネに 鍛冶町のお母さん」 |
店では肝っ玉かあさんで通っている。着物姿にかっぽう着がよく似合う。「体が着物用にできているの。ズンドウでしょ。だから着物がしわにならない」と笑わせる。お酒は一滴も飲めない。「みんな一升びんなんかすぐ開けちゃうって思うみたいだけどまるでダメ。
あと色気のないのが玉に傷かな」と豪快に笑う。「おっかさん、疲れたぁー。かあさんの顔見ればほっとする」と常連客がくつろぐのも納得がいく。店に来た旅行者を、翌日お城や岩木山に案内することもあるという。
面倒みが良く、いつも笑顔が絶えない美枝子さんだが「おしんみたいな子供時代を過ごしたのよ」とほほえむ。 |
美枝子さんの故郷は西郡深浦町横磯。母親は美枝子さんが二歳の時亡くなり、顔は覚えていない。「とても貧乏でした。九人兄弟の末っ子で、兄嫁さんが母親代わりだったわね」。小学校へは兄の子をおんぶして通った。中学の時は朝四時に起きて、ベコの草を刈り、川でおしめを洗い、皆の食事の支度をしてから学校に行ったという。
「中学を卒業したあとは地元の工事現場で働いたんです。モッコで石を運んだり、セメントこねたり。高校に通っている友だちに道路で会えばはずかしくてね」。そのあと「かれご」といって北海道の岩見沢の農家へ奉公に行った。夜明け前に起きて、夜の十一時、十二時まで働き通した。「その家の母さんに可愛がってもらいました。実家に帰るときにはセーター買ってくれて。うれしかったですよ」。
働き者で「気がさがいい」と評判だった美枝子さんは十八歳で望まれて深浦の漁師の嫁になった。だが結婚して一カ月後、台湾坊主と呼ばれた五十年に一度という大きな台風に家も船もさらわれてしまったという。そのあと夫といっしょに生後間もない長女を背負って北海道の港町へ出稼ぎに行ったというからまるで根性ドラマのようだ。
美枝子さんが鍛冶町に「西海岸」を開いたのは昭和六十一年のこと。
「小さいときから食事作りを手伝ってきたし、漁師さんたちの飯場で働いてきたから料理には自信があったの」と美枝子さん。深浦の家庭料理や漁師さんの魚料理が「西海岸」の自慢。イカのごろ炒め、グンナリという海草の入ったすり身汁、若おいのおにぎり、したらみの酢味噌あえ。何を頼んでも文句なしにおいしい。
日曜日は海に潜る。モズクは夏の間に一年分を取ってきて、冷凍庫にしまってある。イクラも自分で何十キロとしょうゆに漬け込んだ。お客さんの喜ぶ顔が何よりと美枝子さん。
「子供たちを抱えて、がむしゃらに働いてきました。子供も一人歩きを始めたし、今が最高に幸せ。これからは自分の人生を楽しく生きていきたいですね」。
お店で食べたおにぎりはでっかくて、ほおばるとやっぱりお母さんの味がした。
| |
|
|
|
| くらしの器・美術「安曇野」オーナー |
平成7年1月7日掲載 |
| 三浦 明子さん |
「何があっても平気!生き方はマイペース」 |
白髪が素敵な女性だ。似合いますね?
「白髪はとても好きですね。きっと好きだから似合うんでしょう。ありのままできれいでいたい。白髪を染めるより、もっと素のままの自分を愛せばいいのにって思っちゃう」。
明子さんは三十歳の時、陶器の店「安曇野」を開いた。出来るわけがないと周りの人たちに言われたらしい。「好きというのがすべて。つぶれたっていいんだって思っていたから、何があっても平気でしたね」と凛とした表情を見せる。 |
明子さんは二十四歳の時一度結婚した。が「結婚生活ではちゃんと自分が表現できないと思った」と言う。二十五歳の時に母が亡くなり、父親の世話をしながらさまざまな習い事をしたが、少しも満たされなかった。父の死後、何かを始めたいと考えた時、大好きだった陶器が浮かんだ。
店内には明子さんが好きな作品しか置かない。作家を訪ねて、明子さんが気に入ったものを仕入れてくる。「会う人会う人いい人ばかりでした。陶芸作家も売れてからでいいよって仕入れではお金を取ってくれなかった。あなたみたいな若い女性がこんなもうからない仕事やってくれるなんてと喜ばれたり」と明子さん。「人は何かをするために生まれてきているんだと思うんだけど、わたしにはこの仕事をしなさいって言われているのかなって思うの」。
強い人だと言われることが多いと明子さんは笑う。「でもこれは自分らしく生きたいと思うからの選択。決して強いという訳ではないんですよ」。明子さんには小学校六年の娘さんがいる。一人で生んで、育ててきた。娘さんが小学校二年生の時、「ママは結婚していないけど、あなたのことを生みたくて生んだんだからね。ママは一人で頑張っている自分のことを偉いと思うよ」と話して聞かせた。娘さんはしばらく考えた後、「わたしもママのこと偉いと思うよ」と言ってくれた。
明子さんは毎日の暮らしを大切にしたいと思っている。お店を始めて間もないころ、年配の女性を見て、年の取り方の違いに驚いたという。「どうしてこう差がつくのかしらって考えて毎日の過ごし方、考え方、生活の仕方じゃないかしらって思ったんですよ」。
毎日の暮らしを大切にして欲しいから、毎日使う器も本当に自分の気に入ったものを使って欲しいと明子さんは考えている。「若い女性がいいって世間が言うのは中年の女性が素敵じゃないからでしょう。若い人が年取ることも素敵って思えるような中年の女性が増えてほしいですよね」。
「楽な方を選ぶんじゃなくて、気持ちのいい方を選んでねと娘にも言っています。何かに一生懸命で、いつもワクワクドキドキしているおばあちゃんでいたいわね」。
白髪って素敵なんだと初めて感じた気がする。歳を取ることも素敵だと思える、そんな先輩たちがどんどん増えてほしい。わたしもそう思う。明子さんのさわやかな笑顔が心に残った。
| |
|
|
|
| 喫茶店「万茶ん」のママさん |
平成6年8月19日掲載 |
| 香西 慶子さん |
「土手町見つめて55年 コーヒーの味守り継ぐ」 |
紫色のストライプのブラウスが決まっている。髪は断髪。「これは自分で切ってるの。後ろは合わせ鏡でちょいちょいってね」。
慶子さん(66)は昭和四年から続く老舗(しにせ)の喫茶店「万茶ン」の二代目名物ママさん。ガイドブックを見ながら、修学旅行生がたくさん店にやってくる。その子たちにお土産にしてもらおうと、今年も弘前城と鳩笛を題材にした絵馬を配って人気を呼んだ。
|
肌がすべすべの慶子さん。若さの秘訣は毎朝のコーヒー。朝の七時半には店を開け、万茶ンのコーヒーを楽しみにしている出勤前のサラリーマンたちとまず一杯。「これが健康のバロメーター。体調で味が変わります。きょうは調子いいな、悪いなとすぐに分かる。うちのコーヒー飲むのがわたしの美容と健康のもとね」。
土手町に住んで五十五年。この町の歴史を見つめてきた。「今、土手町で店張ってる社長たちはみんな幼なじみ。凧上げたり、夜の土手町は子供たちの遊び場だったの」と懐かしそうに話す。蓬莱橋のたもとから木炭バスの後ろにスケート靴を履いてつかまって、一番町の坂の上から滑って降りて来たり。大きな落とし穴を作って、人をおどかしたり。笑顔にやんちゃな女の子の面影が残る。
人一倍元気でお茶目な女の子は、三つ年上の幼なじみ、喫茶「万茶ン」の長男一郎さんと恋仲になる。「両親から反対され、駆け落ちを考えたこともあったのよ。失敗しちゃったけど」と笑う。二十四年に晴れて結婚。初代のハイカラママさんかねさんにコーヒーのたて方を仕込まれた。
「アメリカ育ちの姑(しゅうとめ)は大した苦労した人だったの。
それこそテント張ったような店から万茶ンを始めたんだもの。嫁姑のかっとうもありましたよ。」
毎朝、夫と二人で四季を通して出せるコーヒーを作ろうと研究。さまざまなブレンドを試した。その時出来上がったオリジナルブレンドは今も全く変わらぬ万茶ンの味だ。
昭和三十四年からは喫茶店に加えて、隣りに寿司万という寿司屋も始めた。二店が軌道に乗ったころ、一郎さんが交通事故で亡くなった。慶子さんが三十五歳の時だった。「がんばりへー」と人に言われるのが、一番辛かったと慶子さんは言う。小学校二年と中学二年の息子、お姑さんとの生活を支えるため、慶子さんがやるしかなかった。寿司指導員の免許を取りに職業訓練校に通い、慶子さんが寿司を握った。
「弘前でおなごで寿司握ったのはわたしが初めてかな。今だってその気になれば、包丁一本さらしに巻いて、出稼ぎいってもいいよね」と慶子さん。
一郎さんが亡くなった時小学生だった息子さんが、今は三代目を継いでいる。現在の店で往時をほうふつとさせるのは開店当時から吊るされていたというシックなシャンデリアと官立弘前高校の学生から贈られた木彫りの大鵬、一郎さんの父親が彫ったというレリーフだけ。
「朝お客さんと飲むコーヒーが美味しいうちはまだまだ大丈夫ってみんなに言われます。姑は一郎の形見のコーヒーを飲んで九十三まで生きました。わたしもコーヒー飲んで頑張りますよ」。四十年変わらない一郎さんのブレンドコーヒー。豊かな香りの中で万茶ンの歴史に思いを馳せた。
| |
|
|
|
| 弘前市教育委員会委員子ども人権オンブズマン |
平成7年10月21日掲載 |
| 外崎 ひささん |
「教師の経験生かし 優しくアドバイス」 |
開口一番「女性の記者が取材に来てくれるとうれしくなっちゃいますね。いろんな分野で女性が活躍しているのを見ると、本当にうれしい」と切り出した。女性として新分野で活躍してきたこの人らしい言葉だ。
外崎ひささん(66)は十月一日、弘前市の教育委員に任命された。青森市、八戸市には女性の教育委員が以前からいたが、弘前市では四十年ぶり、二人目の女性の教育委員の誕生だ。「全く思いがけないことで驚きましたが、女性にどんどん活動してもらいたいと市の方から言われて決断しました」 |
弘前市教育委員は五人。メンバーは現在、弁護士、医者、商工関係の人、教育長と外崎さん。それぞれの立場から意見を交わし、さまざまな教育に関する問題を検討していく。
学校教育と社会教育運営に関する方針を定めたり、学校、公民館、図書館などの教育機関の設置や廃止を決定。児童生徒の就学する学校の区域を設定するのも教育委員の仕事だ。
外崎さんは中学校の教員として三十四年、小学校で教頭、校長を経験したベテラン。中学では何の教科を? と尋ねると「ちょっと恥ずかしいんですが、音楽の教師」と照れる。「父が教師でしたので、わたしは学校の中の教員住宅で育ちました。小さいころから学校の音楽の授業を聴きながら大きくなったんです。教室のオルガンに触ったりしながら。それで音楽が好きになって、青森師範学校の芸能科に入ったんです。芸能科なんてタレントさんみたいでしょ」と外崎さんは笑う。
「教師は始めから、一生続けたいと思っていた」という外崎さん。夫のお母さんに子どもを見てもらいながら、働き続けてきた。昭和五十八年、外崎さんは小学校の教頭に就任。「わたしが教頭になった時は市内で女教頭は一人だけ。校長はゼロでした。今は教頭が六人、校長は二人います。女性の指導主事も二人。弘前市も随分変わりましたよ」ちなみに県下では二十七人の女性校長、七十八人の女性教頭が誕生している。
「在職中は女性管理職が非常に少なかったでしょう。
自分がしっかりしないと後に続く女性を出してもらえない、頑張らなければと思いましたね」。ゆっくりと一言一言かみしめるように話す。現在二歳の男の子のおばあちゃんでもある。
仕事の話では厳しい表情の外崎さんだが、お孫さんの話になると目尻が下がる。「失敗だらけの子育てでしたが、母親としての経験も仕事に生かせたらいいですね」。外崎さんは以前から人権養護委員をしていたが、六月には中弘南黒地区で唯一の「子ども人権オンブズマン(子どもの人権専門委員)に任命された。自宅で「子ども人権相談所」を開き、子どもに関する相談に乗る仕事だ。
「相談を伺うと言葉によるいじめが増えています。人間というのは言葉ですごく傷つく。不登校の子も増えてきています。子どたちの思いやりを育てるような活動をしたいです」
毎週金曜日、市役所の市民相談室では人権養護委員がスタンバイし、さまざまな相談に乗っている。「いじめとか不登校など、子どもに関する相談でしたら、わたしのところに直接相談の電話をしてほしい。どこに相談したらいいかしらと悩んでいる人もいるはず。話せば先が見えてくることもあるし、気持ちが楽になります。是非気軽に電話してきてほしいですね」
一見堅い印象だが、えくぼの浮かぶ素顔が優しい外崎さん。教師としてのキャリアと母親の経験を生かし、さまざまな問題を抱える教育界に一石を投じることを期待したい。
| |
 |
|
|
|
|