|
|
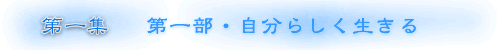 |
スナック「石中家」店主
|
平成7年12月16日 |
| 中原 令子さん |
「何にでも興味をもって 気持ちはいつも28歳」 |
真っ赤なポンチョにジーンズ、くるくるっと巻いた沖縄風の結い髪がトレードマーク。弘前の街を冬でもげたで闊歩(かっぽ)する。ユニークなおしゃれに振り返る人も多い。
だれとでもすぐに友達になってしまうから、観光客と一緒に取った写真は数知れない。「塩沢ときだ、なんて修学旅行の学生さんに言われます。イエイ!ってこたえて一緒にパチリ。わたしの写真、全国に散らばっているわよ」とめっぽう明るい。中原令子さん(64)は桶屋町のスナック「石中家」のママさん。だがだれもママとは呼ばず「石中家の令子ちゃん」で通っている。
令子さんが石中家を開いたのは二十一年前。以来一人で店を切り盛りしてきた。その間さまざまなことがあっただろう。だが、「苦労なんて忘れちゃった」と笑い飛ばす。 |
スナックを開く前は母親と一緒に弘前城の堀端で「石中家」という名のパン屋を経営していた。令子さんが大切にしている「石中家」の名には思い出がある。
令子さんの父親春雄さんは弘前出身の小説家故石坂洋次郎の親友だった。洋次郎の小説「石中先生行状記」の主人公石中の石は石坂、中は中原から取ったものだという。令子さんは父親の思い出が深い「石中」を屋号に決めたのだった。
令子さんが小さいころ、中原家には春雄さんを慕って役者やボクサーなど風変わりな人が出入りしていた。「父は洋服屋でしたが、女性の着物コートを作って売ったり、ユニークな人でした。冗談がきつくて、女の人は全部自分の彼女だってしゃべっちゃう。好きなように生きた人でしたね。その血はわたしに引き継がれているって人に言われます。父そのままだって」
石中家はこぢんまりとした店だ。店内には令子さんが集めたり、お客さんからもらったという小さな人形、ガラス細工がたくさん並んでいる。「わたし、体は大きいけれど、こんたちっちゃなものが好きなの」と米粒ほどに小さいおひなさまを見せてくれた。繊細な人なのだろう。高齢の母親を気づかって、自宅への電話を欠かさない。
店内を見回すときれいな「押し花絵」が飾られている。令子さんの作品だ。朝早く起きて自宅の周りを散策し、野の花を摘むのが令子さんの楽しみ。摘んだ花を押し花にし、デザインして店に飾る。「小さいころから押し花が好き。遠足に行くと、花を取ってきてノートに挟んでおきました。NHK文化センターの押し花教室の第一期生なんですよ」。
来年は同センターで始まるフラダンスの教室に通う予定。「たいぎだ、たいぎだって思えば本当にたいぎになっちゃう。六十過ぎたからと思えばその年になっちゃう。わたしは常に二十八歳のつもり。何でも興味もって楽しんでやらないと」。これが若さの秘訣(ひけつ)だろう。ねぷた期間には店を休んで太鼓をたたく。さらしをぎりっと巻いて、諸肌(もろはだ)脱いで、大太鼓をたたく姿は粋(いき)。弘前の姐後(あねご)といった感じ。「ますます恋をして、頑張りますよ」。かんざし代わりに髪に差した津軽塗の茶しゃくがきらりと光を放っていた。
| |
|
|
|
| 陽光ファームいわき |
平成9年5月24日掲載 |
| 田村 真裕美さん |
「無農薬・無肥料で農業自然に逆らわず土に感謝」 |
新緑の岩木山がすっきりと見渡せる岩木町葛原に田村真裕美さん(36)の田んぼと畑はある。きょうは小学校二年生の陽奈ちゃんと一緒にキャベツの苗植え。真裕美さんは農薬、除草剤を一切使わない。その上、無肥料、無堆肥という常識を覆すやり方で農業を展開している。
「わたしはあくまで作物の手助けをするだけ。植物は自らの子孫を残すために自分の生命力で実りますから」と穏やかに話す。真裕美さんと共に畑に入ってみた。土を踏むとフワフワとした柔らかい感触。畑の生命力を感じる。真裕美さんはひとつの畝にキャベツの苗、長ねぎ、大豆を植えていく。
|
「大豆の根粒菌が土を豊かにしてくれ、長ねぎはにおいを嫌い、虫が寄って来ない。雑草にはワラを敷く。夏場は作物と雑草が共存です」。苗を植ながら、真裕美さんは「キャベツさん頑張って」と苗に声を掛けていく。野菜は声を聞いているのだと真裕美さんは言う。「畑サ入れば、不平不満は言わないことにしているの。野菜サ聞いていてひねくれるんだもの。うちに来た苗は幸せだよ。農薬は掛けられないし、言葉は掛けてもらえるし」とにこやかにほほえむ。
真裕美さんが本格的に農業を始めたのは五年ほど前。それまで一人で頑張ってきたお母さんが体を壊し、真裕美さんが農業を継ぐことを決めた。子供たちには安心できるものを食べさせたいと考えていた真裕美さんは無農薬での栽培に踏み切った。
同町五代で無農薬の栽培をする木村秋則さんに農具の使い方、畝の作り方、畑の耕し方など一から教わった。一九九三年の大凶作にも真裕美さんの田んぼではたわわに稲が実り、近所の人を驚かせた。「無農薬、無肥料だと今に取れなくなるよと言われ続けたけれど、収穫した物を見て、皆納得してくれます」。
今では真裕美さんを中心に女性ばかり十人が集まってグループ「陽光」を作り、真裕美さんの畑を借りて野菜の無農薬栽培を始めた。メンバーにはサラリーマンの奥さんなど農業は初めてという人もいる。
「今、若い人たちに足りないのは土や自然に触れること。土に触っているといろんなことに気づかされる。自然に逆らわず、大地をけがさないようにしたい」と真裕美さんは言う。
夏場は草との闘いだ。田んぼではアルミの手押しの除草機を使い、草を採っていく。「大変でしょ」と言えば、「実る姿を見れば、やってて良かったと思う。お客さんにおいしいと言われた時の喜びは大きい」。宣伝はしないが、おいしいという評判が口コミで広がり、県内の消費者グループと契約して米と野菜を出荷している。「野菜の色も味も全然違うの。食べたい人は収穫時期に遊びに来て」と真裕美さん。採れたてのホウレンソウをもらって帰り、土鍋で湯がくそばからしゃぶしゃぶ風に食べてみたところ、ホウレンソウの野性的な味と香りが口いっぱいに広がった。
「土への感謝の気持ちを大切に、自然に逆らわないようにしていると自然が味方してくれる。若い人がこういう農業だったらやりたいなって思ってくれるようになればいいね」と明るい笑顔を見せる。畑仕事を終えて帰る時、陽奈ちゃんと一緒に「畑さん、失礼します」と土に話し掛けていく。土とも友達になってしまう真裕美さんの正直で柔らかい心が、きっと野菜にも伝わるんだろうなと、本当にそう思った。
| |
|
|
|
| 民芸店「おくせ」オーナー |
平成8年5月18日掲載 |
| 奥瀬 陽子さん |
「心和む作品目指し 鉄則こけしを継承」 |
桜の散る季節、城下町黒石の民芸店「おくせ」を訪ねた。店のオーナーでこけし工人でもある奥瀬陽子さん(52)に会うためだった。 黒石の町並みを過ぎ、緑の多くなる辺りに「おくせ」はひっそりと建っている。店の前には花が植えられ、女性の店らしい華やぎが伝わる。のれんをくぐると、ほっそりとした女性が笑顔で迎えてくれた。
メキシコのガラス、インドの木彫り、トルコのキリム、益子の陶芸など店内には陽子さんが集めた色とりどりの民芸品が並ぶ。「夫が愛した民芸とこけし、好きな物に囲まれて暮らすわたしは幸せ者です」と陽子さん。
|
居間には二百五十本のこけしが飾ってある。鳴子、遠刈田、福島、山形、岩手、そして青森の温湯こけし。その中には陽子さんの夫でこけし工人だった鉄則さんの「泣きべそこけし」も愛らしい顔を並べていた。鉄則さんが亡くなって四年。二年前から、陽子さんはこけしを作り始めた。
陽子さんは午後、ろくろの前に座る。「主人の仕事をずっと見続けてきたことが導きになりました。主人の姿を思い浮かべて、ああこんな風にやっていたなとなぞりながら作っています」。鉄則さんが残した原木をチェンソーで切断し、ナタを振るって木取りをする。木取りしたものをろくろに打ちつけ、カンナで削って形作っていく。
「最初の一本、二本は形になりませんでした」と笑う陽子さん。ペーパーで磨き、彩色。そのあと顔を描いていく。顔を描くのは難しい。まゆ一本、鼻の大小で表情が変わる。目元、口許の描き方で笑い顔になったり、泣き顔に変わったり。「主人のこけしは泣きべそこけしと呼ばれていますが、わたしのは笑い顔になちゃうんです。主人のこけしに似せようと思っても似ませんから、これはやっぱりわたしのこけし」と照れた。
二年で百四十本のこけしを作った。最初に出来上がった作品は鉄則さんの仏壇に供えたという。作った作品はすべて写真に取って残してある。アルバムのページをめくると、あどけない表情のこけしがにっこりとほほえみ掛けてきた。
「この年でいい作品を作るというのは無理かもしれません。ただ、お客様が楽しんでくださればうれしいんです。この店を開く時も主人と二人、そういう気持ちで始めましたから」。取材中にも、友人にプレゼントを、という男性や女子高生がコーヒーカップやグラスをゆっくりと選んで買っていった。「今、わたしが寂しい思いをしなくてすむのは、主人がお客様や友人をたくさん残していってくれたから」と陽子さんは言う。
民芸店「おくせ」の居間はサロンのよう。民芸を買いに来たお客さんがここでおしゃべりを楽しんでいく。笑顔がすてきな女主人の魅力のなせる技でもあるのだろう。こけしの話に花が咲く。「目標は鉄則こけし。近づきたいけど無理でしょうね。盛秀太郎先生から主人が引き継いだこけしを継承していけたらいいですね。見てほっとする、気持ちが和むような、そんなこけしを作りたい」と顔をほころばせる陽子さん。「鉄則はいなくなっても、こけしを作っているかぎり一緒にいられる、そんな気がしています」と少女のような笑顔を見せた。
| |
|
|
|
| 三ツ矢交通グループ取締役会長 |
平成6年8月20日掲載 |
| 工藤 茂子さん |
「亡き夫の言葉が支え 今は毎日が幸せな日々」 |
ひと目見ると大輪のバラというイメージ。そう言うと「私は色気ないし、男っぽいんですよ。もう仕事ひと筋」と言って笑った。工藤茂子さんは三ツ矢タクシー、三ツ矢自動車学校を経営する三ツ矢交通グループの取締役会長だ。
昭和五十一年にご主人が亡くなって以来、当時大学生だった息子さん二人を育てながら、会社を経営してきた。「身内は三人だけと思うと心細くて仕方ありませんでしたよ。それまでは守ってくれる人がいたけど、これからは一人で立ち向かわなくてはいけないんだから」。それでも存命中「一番を目指すんだ」と常々言っていたご主人の言葉を思い出し、負けないで頑張ろうと心に誓ったという。 |
「主人が亡くなって私は変わりましたね。強くなった。当時人に会うと、茂子さんは眉毛がつり上がるってよく言われましたよ。女だからって馬鹿にされまいといつも思っていました」
そんな中で仕事に関して困らなかったのは主人のお蔭、と茂子さん。学校を出てすぐに結婚し、何もわからなかった茂子さんを夫の武房さんはどこへ行くにも連れて行った。仙台の陸運局へ申請に行くにも、銀行に行くにも茂子さんを伴った。
自宅と会社が一緒だったので夜中の電話番は茂子さんの仕事。なりふり構わず働いた。「長男が幼稚園のころ、参観日にスカート履いていったの。そしたら息子がワーっと寄ってきて、足にさわるんですよ。それくらい私のスカート姿が珍しかったのね」と笑う。
タクシー数台から出発した会社は、現在浪岡、青森にも会社を持ち、タクシー総数二百五十三台を数えるまでになった。
茂子さんはこの夏、孫の紀篤くん(中二)と富士登山に挑戦する。「五合目から登るんです。六十歳の記念ですよ」と嬉しそう。孫の話になると、とたんに眉毛が下がる。お孫さんが小学校一年生になった時、家族全員を集めて「これからは名前を呼んでね」と頼んだ。だから孫たちは親しみを込め「茂子ちゃん」と呼んでいる。
茂子さんの楽しみはコーラスと十五年続けているアートフラワー作り。それとやっぱり仕事。「来世は男に生まれてバリバリ仕事をしたいわね。そして主人は女になってもらって、今度は私が大切にしてあげたいわ」。息子さん二人、娘のように可愛がっているお嫁さん二人、孫三人の家族に囲まれて、幸せいっぱいの笑顔を見せた。
| |
|
|
|
| 花ことば |
平成7年1月7日掲載 |
| 北畠 美貴さん |
「人も花もナチュラルがいい花と一緒にあそびましょ」 |
外は冷たい風が吹いていても、花屋さんの店内はすっかり春。甘い香りのフリージア、華やかなラナンキュラス、オレンジ色のサンダーソニア。
おしゃれな雰囲気の青い花はブルースター。花たちに囲まれて幸せそうにほほえむのは「花ことば」の美貴さん(38)。
「市場から仕入れたばかりの花の箱を開ける時が一番幸せ。でも花屋の仕事は見た目より重労働。流産しかかったこともありますよ」。バイトの女子大生に間違えられる美貴さんだが、実は大地くん(11)、杏(あんず)ちゃん(8)、花梨(かりん)ちゃん(6)、拓海(たくみ)くん(2)の合わせて四児のママ。赤ちゃんが生まれる前日まで働いていたという彼女。髪はボブ、ノーメイクにジーンズといういたってシンプルなスタイルが美貴さん流だ。 |
「長野県の中央アルプスと南アルプスに囲まれた町で育ったので自然が大好き。花も自然な感じにアレンジしたい」と話す。「花ことば」の店内には美貴さんはじめ、女性スタッフがアレンジした花かご、ブーケ、寄せ植えが並ぶ。
美貴さんが夫の和彦さん(39)と弘前に店を開いたのは十年前のこと。長野で小学校の教諭をしていた美貴さんにとって花を扱うのは初めての経験だった。
「聞かれても花の育て方は分からないし、津軽弁は聞き取れないし。づき(肥料)けって言われてもなんのことかチンプンカンプン。生後三ケ月の大地をおんぶしながら本を片手に悪戦苦闘。若かったからできたんでしょうね」。
そんな美貴さんも和彦さんを師匠に、今では花のオーソリティー。市場で指を使い、花の仕入れをするまでになった。午後、美貴さんは花ごとに水揚げをしていく。花によって水揚げの方法が異なる。「お客様がけがをするといけないから」とバラの花は一本づつトゲを取り、葉を整え、茎を切ってからサッとお湯に通す。 丁寧な水揚げは手間が掛かるが、花もちが全く違う。「ユキヤナギなど枝ものはカナヅチでたたきます。せっかく買っていただくんだから、長く花を楽しんでほしいから」
花を扱う美貴さんのつめは草花のアクで黒づんでいる。「子供たちの参観日に行くとほかのお母さんはきれいにマニキュアをしていて、思わず指を隠しちゃう」と笑うが、子供たちには自慢のお母さんの手だ。
気軽に花を楽しんでほしいと、二年前から「花あそびの会」を始めた。「免許を取るとか目的を持たず、毎週一回花と一緒に遊ぶ会。ドライフラワーのアレンジメント、リース、コサージュ、ハーブや観葉植物の寄せ植えなど。生徒さんと一緒に楽しんでいます」
「花なんてなくても生きていける。なくても困らない。でもお花が一本あるだけで優しい気持ちになれる」と言う美貴さん。バレンタインデー、ホワイトデー用にハート型のアレンジメントも計画中。贈る相手の雰囲気に似合った花束も美貴さんが作ってくれる。優しい気持ちを添えて花を贈れば、相手にもなんだか思いが届きそう。
「お花って頑張っている自分自身へのごほうびって感じ」という美貴さんの笑顔に誘われて、わたしも白いラナンキュラスを三本、自分にプレゼント。
| |
|
|
|
| 弘前市立和徳幼稚園「ことばの教室」講師(臨床心理士) |
平成9年3月15日掲載 |
| 吉川 ちひろさん |
「カウンセリングの勉強に子連れでカナダへ留学」 |
「人間の心って砕くのはとても簡単。でも心のケアにはとても時間が掛かる。カウンセラーは花が咲くのを待つだけ。そばにいて待つことの大切さを学びました」。静かにゆっくりと、吉川ちひろさん(53)は言葉を選びながら話す。
弘前市立和徳幼稚園内の「ことばの教室」でちひろさんはカウンセリングを担当している。弘前市川先の自宅から雪の中、自転車を飛ばして幼稚園までやって来る。
「ことばの教室」には言葉の遅れた子供、ダウン症、自閉症などさまざまな問題を抱えた子供たちが両親と共にやって来る。積木や人形、ボールを使って遊ぶ子供たちの姿から、子供たちの心の状態を知ることができるという。 |
「日本は頭がいい人、学歴のある人が日の目を見る社会。もっと人権とか心を大切にする世の中になってほしい。そしてスクールカウンセリングという仕事の大切さや必要性を知ってほしいですね」と話すちひろさん。そんな思いからカウンセリングを学ぶために過ごしたカナダでの留学生活を「モントリオールの学校で」という一冊の本に著した。
ちひろさんは国際キリスト教大学大学院で教育哲学を学んだ後、仙台の中学と高校で英語の教諭をしていた。「駆け落ちした生徒を探すために夜汽車に乗ったり、不登校の生徒を説得したり。生徒の気持ちが良く分かっても、それを生徒にどう伝えたらいいのか、迷うことも多かった。カウンセリングの勉強をしたいと思い始めたのはそのころですね」
十八年前、夫と共にやって来た弘前で、大学の心理学科の聴講生となった。「ちょうど妊娠中で大きなおなかを抱えて通った。なんでこんなおばさんがいるんだろうなんて若い学生に思われながら四十歳まで六年間勉強しました」というしなやかな努力家だ。
その後、市の児童相談所の嘱託判定員として子供たちの発達に関する相談にのってきた。三歳児の検診では母親からさまざまな悩みを相談された。「育児の苦しさを誰に話していいのか分からず、いすに座っただけで泣き出す母親や、言うことを聞かないから子供をなぐってしまうという若いお母さんもいました」。深刻な問題を抱えるケースが多くなり、行き詰まりを感じたちひろさんはもっと本格的にカウンセリングの勉強をしたいと、一九九〇年、小学生の娘さんを連れてカナダへ渡った。
「北米はカウンセリングの先進国。カウンセリングそのものを勉強したくて、ロータリー財団の奨学制度に応募したんです」。四十六歳での挑戦だった。著書にはカナダのハイスクールでスクールカウンセラーとして現場研修した体験が丁寧につづられている。家庭内暴力、離婚、虐待、セクハラ、さまざまな問題を抱える子供たちと過ごした経験はちひろさんをひとまわりたくましくした。
「それまではうんうんと聞くだけでしたが、カウンセラーも強さが必要だと分かりました。我慢すれば?と流されるのではなく、少しでも社会を変えていこうという強さを持たないといけません」と言い切る。
「日本の子供たちもいじめや自殺、不登校、体罰など厳しい状況に置かれている。何か悩みがある時、カナダの生徒たちはスクールカウンセラーの前で心の重荷をおろし、自分を取り戻すことができた。日本の学校にもそんな場所が必要。この本がそんな状況作りの手助けになれたらいい」と静かに話すちひろさん。
小さいころから自分自身、心の中に引きこもるタイプだったと自己分析するが、カウンセラーという仕事を通して、強く、たくましくなったちひろさんがそこにはいた。
| |
|
|
|
| 珈琲舎「あすなろ」オーナー |
平成10年1月24日掲載 |
| 大川 京子さん |
「あこがれの街 弘前でくつろぎの空間演出」 |
外は激しい雪。息を切らしてドアを押すとコーヒーの香りが優しく顔を包む。店内には白いフリージア、薄紫色のスイートピーが飾られ、穏やかな雰囲気にほっとひと息。この空間をプロデュースするのが大川京子さん(57)。
コーヒーのカップはひとつひとつ違う。京子さんが好きで集めたものを客人の雰囲気に合わせて供す。わたしの前には小花のカップ。紫と白の小さな花がカップの表で揺れている。「一人でいらっしゃる方が多いんですよ。ホッとしに来る方、話を聞いてほしい方」。
京子さんの落ち着いた雰囲気が何でも話せるような、そんな気分にさせてくれるのだろう。京子さんは小樽の生まれ。「娘時代に遊びに来て以来、弘前はあこがれの街でした。駅に降り立つと空気がほっこりとしていて優しい街」
いつもは聞き役の京子さんだが、きょうはテーブル越しに一人語り。降りしきる外の雪を眺めながら、京子さんの話に耳を傾けた。 |
小学校三年の年、刑務官だった父親の転勤で青森市にやって来た。荒川の田んぼの中にぽつんと建つ刑務所と官舎。「言葉が分からなくていじめられっ子でした。荒川中学で出会った北彰介先生と一緒に演劇をしたのがすてきな思い出」
高校を卒業すると国鉄バスのバスガイドになった。「ツバメのマークの帽子がかっこよくて。当時、女性の花形の職業でした」。だが見ると聞くとでは大違いだったという。始発に乗るためには午前三時半の起床。バスの清掃もガイドの仕事だった。余りに厳しい労働条件に女性たちで労組を作り、当時の新聞をにぎわせたこともあったという。ガイドをしながら見た街の小さな店。いつかそんなお店を持つのが京子さんの夢だった。
結婚、子育て。子供たちが小学校に上がるようになると自分だけおいてきぼりになるような思いになったと京子さんは笑う。「手作りのおやつを作って待っていても、子供には子供の世界ができ始めた。このままだと自分だけ取り残される。何か社会と係わっていきたいといつも求人欄を見ていました」
そんな時に飛び込んできた化粧品販売の仕事。「主人は猛反対。でもここで引き下がったら一生このままだと頑張りました」。内緒で仕事を始めた。半年後、初めて十万円を稼いだ妻に、夫は「お前もなかなかやるな」と承諾。それまで右を向けと言われればずっと右を向いていたという京子さんの人生が一転した。ただ単に化粧品を売るのではなく、皮膚構造から勉強し、トータルアドバイザーになりたいという強い意思と努力で京子さんは二年後、営業所長になる。
十年は続けようと頑張った十年目。京子さんは販売の仕事を辞めることを決めた。「冬は歩き、夏場は自転車。所長になっても自らお客様を開拓していくというやり方に体力的な限界を感じました。収入はあったけれど生はんかには続けたくなかった。マンネリは嫌なの」と京子さんは笑った。
花が大好き。「あすなろ」を始めて十一年になるが花を欠かしたことがないのが自慢だ。「ここにいて、居心地のいい空間を作ってお客様を待つ。降る雨や雪を眺めたり、いろいろな人生をみつめたり」。十一年間、毎日欠かさず通ってくれるファンもいる。十年目で大病を経験したが、そのお蔭で一日一日の大切さを知ったとほほえむ。
今年から店内でギャラリーも始めた。花と絵と京子さんの笑顔、そして主役のコーヒー。ミニコンサートやお話会。そんな企画も立て、いつかサロンとしてみんなに使ってもらいたい。二十周年に向けて、大きな夢を広げている。
|
| 2003年8月25日没 | |
| |
 |
|
|
|
|