|
|
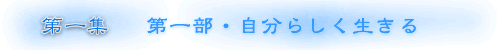 |
五所川原市「働く婦人の家」館長
|
平成10年10月24日 |
| 芦田 ふみえさん |
「しっかり地に足をつけ 女性支援に力を尽くす」 |
県内には青森市、三沢市、五所川原市の三カ所に「働く婦人の家」がある。一九八三年にオープンした「五所川原市働く婦人の家」の初の女性館長として五年前に就任。四月に開設した県内初のファミリーサポートセンターの設置にも大きな役割を果たした。
ふっくらとした顔立ちと体型が相手に安心感を与える。何が来ても平気といった負けん気の強さが芦田ふみえさん(59)の魅力。「うちの館長は男のようですって部下がしゃべります。長い物に巻かれるのは大嫌い。おなごのくせになんて言われればムカつくよね。子育てや老人介護のために女性に仕事を辞めさせることは絶対にできません」 |
ゆっくりと、確実な言葉が返ってくる。だが五年前、館長にと指名された時は足が震えたと笑う。六〇年に弘前の東北栄養専門学校を卒業。すぐに五所川原市役所の職員として西北病院の栄養士となった。学校給食、養護老人ホーム、病院の栄養士として三十三年間勤めた。そして異色の抜てき。緊張とストレスから半年間、過敏性大腸炎に苦しんだ。
「それまでは代々、男性が館長を務めてきた。初の女性館長でしょ。なんでこんな人が来たのって感じだったんじゃないかしら」と当時を振り返る。同僚女性の励ましに支えられて、ここまでやってきた。芦田さんが何よりも始めたかったのは老人介護の講座と保育講習会。女性だけが負担を抱えるのではなく、地域ぐるみで子育てや介護の問題に取り組みたいというのが願いだった。
それがかなったのは今年の四月。県内初のファミリーサポートセンターが五所川原市にオープンした。子育てを手伝ってほしい会員と手助けしたい会員をつなぐセンターの存在は一人で子育てする若いお母さんの大きな味方となった。
「できるだけ低い資金で開設できるよう計画書を作ったんです。こんな資金で運営できるのかと労働省でも聞かれた。でも市税を使うんだから無駄なお金は使えない。みなで協力すればやっていけると確信していました」と芦田さん。四月の開設以来、同センターは低い資金で高い利用率を誇り、全国でも高い評価を受けている。
「地道にやって少しづつ積み上げていくことが大切。箱作り、ハード面にお金を使うのは男性的考え」と芦田さんはきっぱり。ここには主婦としての芦田さんの感覚が生きる。「女性が参画することの意味はここよ。女性のソフト面での考え方がプラスされれば、すごいことができるんじゃないかしら」
「人一倍、頑張って仕事をしてきた」と話す芦田さんにはもうひとつの人生がある。故あって、一人で子供を生み、育ててきた女としての人生。「順調に行けば、人の気持ちの分からない人になっていたかもしれない。悩んで、悩んで、そんなことがあったから人の悩みや話を聞くことができ
るのかなとも思います」
娘さんは母と同じ専門学校の二年生。母と同じ道を歩みつつある。「娘を産んでよかったとそう思っています。娘がいるから頑張れた。これがわたしの人生なのかなって思います」
今でも憤りを覚えることがいっぱいあると語調を強める芦田さん。「働く婦人の家という名を男性も気軽に入館できる名前に変えたい。女性って名を付けるのは男性差別。すべての年齢の人が使え、男女の区別のない、バリアフリーの施設を目指さないとね」
退職までの一年半、悔いのないよう懸命に頑張りたいと芦田さんは笑った。静かな笑顔だった。
| |
|
|
|
| 月刊「弘前」編集長 |
平成6年7月23日掲載 |
| 青木 美也子さん |
「コツコツと継続15年 体力勝負で奮闘中!」 |
ビルの三階に月刊「弘前」の編集室はある。取材で訪れた日、編集長の青木美也子さんは日の光が入らないうす暗い部屋で書き物をしていた。
編集室はどんな所と見回すと、シンプルこの上ない部屋だ。「ファクスもコピーもワープロもないから、来た人はここが編集室ってびっくりするのよ」と青木さんは笑う。部屋にはデスク二つと昔ながらの黒電話が置かれ、ギャラリー案内の絵はがきとポスターが唯一の飾りだ。そのデスクももらいものとかで「新しい物と言えば「弘前」の最新号だけよ」とにっこり。
この七月で「弘前」は創刊から十五年が経った。「弘前という名前を付けるからには弘前の文化や生活をきちっと載せて、きちんとした文章の本にしたかったですね。そしてバックナンバーを揃えてもらえるような雑誌にしたいなと思いました」と青木さん。今もその編集方針は変わらない。 |
創刊号を見せてと頼むと「エーッ、やめましょうよそれは。すーごく恥ずかしいわよ」と笑う。「作り方がこなれてないし未熟。それとかなりの気負いがありますね、今思うと」。創刊号の巻頭は高木恭造さんの詩「津軽女」が飾った。
青木さんは小さいころから文字に接するのが好きな女の子だった。高校では文芸部に入り、詩や小説を書いた。弘大でも文芸部に所属し、「弘大文芸」を編集した。卒業後、国語の教師になるが一年でやめ、夢だった出版の仕事に就く。「やっぱり編集の仕事が好きなんですね。本を作っていると楽しいんですよ」。
仕事はせっぱつまるまでやらない。ぎりぎりになってワーッと書くのが性にあっている。失敗もたまにはある。座談会の取材でカセットテープに録音したはずが電源が入っていなかった。びっくりしたが「ま、なんとかなるさ。機械なんかには頼らない。頭に入っているさ」と思ったというからすごい。度胸ありますね?
「そりゃ度胸はありますよ」と胸を張る、結構豪気な女性なのだ。
「男っぽいと言うかさっぱりした性格」と七号から共に仕事をしてきた藤田きみさんは青木さんを評する。二人だけで取材から広告取り、営業、集金、配本までこなす。
土手町は台車をごろごろ引いて配本するという。市内もほとんど歩いて配る。郵送はしない。顔を見て配りたいという気持ちからだ。協賛店の人にも月に一度は顔を合わせたいと直接持っていく。
「みなさんに支えられている雑誌ですから。十五年ずっと協賛店になっていてくれる所もあります。弘前は書き手もたくさんいるし、書いてくれる人がいなくて困ったなんてことは一度もないですね」
とにかく長く続けたいというのが青木さんの願い。体力勝負、歩ける限りやりますよと気炎を吐く。弘前のタウン誌として、人、文化、歴史、そんな弘前らしさを拾い上げていってほしい。
| |
|
|
|
| 「夢・音楽サークル」を金木町で主宰 |
平成9年6月28日掲載 |
| |
「本物の音を子供に母親の思いを結集」 |
金木町の三人の女性が今、弘前の町で孤軍奮闘している。夢・音楽サークルを主宰する新岡恵美子さん(47)、荒関映子さん(49)、生玉悦子さん(42)の三人。七月二日午後六時半から弘前市民会館で開かれる県出身のオペラ歌手小渡恵利子さんのリサイタルに向けて全力疾走中だ。
「苦学して音楽をやり通してきた小渡さんの強さとあの素晴らしい歌唱力にほれ込みました。こういう人を応援していくのがわたしたちのサークルだと考えて今回のコンサートを企画しました」。小渡さんと言えばテレビのCMの中で「だいじょうぶー」と
美声を聴かせている、ちょっと太めの女性。
音楽・夢サークルは音楽好きの三人が金木の子供たちに「本物の音」を聴かせたいと始めた。月々三千円づつ積み立て、最初はバスをチャーターして弘前や青森、黒石で開かれるコンサートに子供たちを連れて行った。だが音楽を聴いているうちに自分たちでも音楽会を開いてみたいという思いが生まれ、九〇年に初めてのコンサートを金木町の南薹寺で開いた。 |
手作りのポスターにチケット。休憩時間にはメンバーお手製のそばやちらし寿司もふるまわれるアットホームなコンサートだった。金木町はもちろん、近隣の町村から約三百人が本物の音を聴きに集まった。アルパとギターの夕べ、バイオリンとチェロ、弦楽四重奏、ピアノコンサートとさまざなな企画が生まれた。
「お寺って音響がいいの。演奏者の中にはカーネギーホールにも負けないと言ってくれた人もあったのよ」と元気な新岡さん。「子供たちは口をワーッと開けて目の前の演奏家を見つめていたね」と荒関さん。「三百人分の座蒲団を屋根に干したり、子供たちにおやつを出したり、楽しかった」と生玉さん。いい音楽を聴きたい、子供たちに聴かせたいというお母さんたちの思いがすてきなコンサートを生み出していったのだろう。
三人は三様の性格の持ち主。「思い込んだら考える先に飛んでしまう」という新岡さんはパワフルな情熱家。「こまやかな心遣いの人」と他の二人が声を合わせる荒関さんは病気がちだったが、「夢サークルが支えとなってすっかり元気になった」とチャーミングな笑顔を見せる。開創四百年
の南薹寺を切り盛りする生玉さんは都会的な雰囲気のちょっとシャイな女性。共通点は音楽が大好きな点ひとつ。そんな三人が今燃えているのが小渡さんのコンサートだ。
三人は弘前市内の知り合いや高校時代の同窓生に一人ひとり手紙を書き、紹介を頼んだり、チラシを置いてもらえるよう頼んで歩いている。千三百席の弘前市民会館を満席にするのが夢だ。「小渡さんには音響のいい、大きな会場でおもいっきり歌ってもらいたかった」と声を合わせる三人。
「あの人たち余裕あるからやっているんだと言われるけれど、持ち出し一方。ただの主婦だものバックも何もない。今だって人が入ってくれるか心配で心配で、やらなきゃ良かったって三回くらい思ったよね」と顔を見合わせて笑う。
月々三千円の積立てから今回もバスをチャーター。金木町を四時半に出発し、五所川原市を経由して弘前に向かう。「芸術家を育てるのは庶民だと思っているの。弘前でのこんな大きなコンサートはもう二度と企画できないと思うから思いっきりやるだけ」という三人の熱い思いに共感。七月
二日、弘前市民会館を音楽大好き人間たちで埋め尽くしたい。
| |
|
|
|
| 「女性学」の研究者 |
平成6年4月16日掲載 |
| 佐藤 恵子さん |
「悩み持つ 女性の支えになりたい」 |
センスのいい着こなし、理路整然とした話しぶり。シャープな女性という印象だ。自信とキャリアを感じさせる。そう言うと「とんでもない。迷いながらここまで来たのよ」という答えが返ってきた。
四月からNHK文化センターで全国に先立ち「女性学」の講座が始まる。その講師が佐藤恵子さん。数少ない女性学の研究者だ。「女性学」とは耳慣れない言葉だが何?と問えば
「女性がより良く生きるにはどうすればいいかを探る学問」と教えてくれた。 |
女性ならだれでもぶつかる問題、例えば就職、結婚、出産、育児、家事、女性ゆえの差別などについて、さまざまな視点で考えていく。「決して難しいものじゃない。あなた自身、そして私自身のことでもあるのよ」。
恵子さんが「女性学」と出合ったのは、今から十六年前。大学院卒業後、故郷の名古屋で働いていた恵子さんは、結婚を機に仕事を辞めた。そして専業主婦に。仕事に未練がなかったわけではないが、それが当たり前だと漠然と思っていたという。そして夫の仕事の都合で弘前へ。
初めての子育ては、娘時代に思い描いていたものとは全く違っていた。子供と二人きりの閉ざされた空間。「社会と切り離され、息が詰まりそうだった」と恵子さんは当時を振り返る。大学院で共に学んだ夫は教職に就いた。なぜ私だけが家事、育児をし、夫は手伝わないのか。子育てを苦しいと感じる自分はおかしいのだろうか。自分を責めてノイローゼになりそうだったという。そんな時、出合ったのが「女性学」だった。決して自分だけの問題ではなく、女ならだれでも感じる理不尽が、社会にはたくさんあるとその時知った。
赤ん坊を抱えながらも何かしたいと考え、県の家庭教育相談委員になった。小さい子を持つお母さんの悩みを聞く仕事。それが恵子さんの社会復帰の第一歩だった。
「家庭の中では、夫との対等な関係を求めて奮戦したのよ」と苦笑い。初めは抵抗を示したダンナサマも、長い年月をかけての話し合いの末、変わった。今では人生のパートナーとしてお互いを認め合う関係だ。
「女性学」をライフワークと決め、こつこつと研究を続けた恵子さんは、二年前から弘前学院短大で「女性論」「家族問題」などを教えている。その研究心の底にあるのは、自分自身の苦い経験なのだろう。
「さまざまな壁にぶつかる、女性の支えになれたらうれしいです」。夫と二人で買い物をし、食事作りも臨機応変に分担しているという佐藤家。子供たちも家族の一員として家事を受け持つ。男女共同参画型家庭の見本と言ってもいいかも。
パワフルで機関銃のように威勢のいい恵子さんだが、銃後には家族の温かい励ましがあるのだと感じた。弘前ではまだまだ、こんな家庭は少ないかもしれない。女性たち一人ひとりが元気に輝くためには、男と女の意識の改革が必要なのだと感じた。
そのためには、女たちが共に手をつなぎ、支え合うこと。そこから生まれてくる力に期待したい。
| |
|
|
|
| 画家・女子美術大学教授 |
平成8年8月24日掲載 |
| 佐野 ぬいさん |
「青の魅力に引かれ 青色の世界を描く」 |
今年の二月、パリで初の個展を開いた。パリの新聞はぬいさんの絵を「日本の青い雪」と評したという。パリでの個展を再現した作品展が十五日から十九日まで弘前市上瓦ケ町のギャラリーデネガで開かれ、会場に佐野さんを訪ねた。
絵にはnuitとサインがある。フランス語で夜、闇という意味だ。「若いころはぬいなんて年寄りじみた名だと思っていましたが、今は気に入っています」と大きな目を見開く。会場は全体が海の底に沈んだような印象だった。それも南の海。太陽の光が底まで届くような透明な海だ。優しさ、暖かさ、静かさ、冷たさ、さまざまな表情を持つ青色が波打ちながら、光の中で揺れていた。佐野ぬいさん(63)は青に魅せられた画家だ。 |
「青は不思議な色。水や空の色だけど光の屈折でそう見えるだけ。わたしにとっては麻酔のようなもの。描いているうちに恍惚(こうこつ)となったり、引き寄せられたり」
弘前市百石町で育った。父親の繁さんは和洋菓子の店ラグノオを経営しながら絵を描き、詩を書く粋な人だった。父親の経営する喫茶店には石坂洋次郎、棟方志功らが遊びに来て、芸術談義に花を咲かせていたという。
弘前中央高校在学中に、絵の道に進もうと決めた。「父の影響が大きかったですね。パリにあこがれ、絶対絵かきになってパリに行こうと思いました。石坂洋次郎先生には女の絵かきなんて嫁に行けなくなるよと言われましたけど」とほほえむ。「『お前なら大丈夫。何をやってもいいよ』という父の言葉がその後のわたしを支えてくれました」とぬいさんは言う。
女子美術大学芸術学部で絵を学んだ。卒業後は助手として大学に残った。二十五歳で結婚。だが、子育てをしながら、大学で教え、自分の絵を描いていくという生活は大変だった。子供を生んだ後、大学から「三岸節子のように有名になったら迎えにいきます。今は子育てに専念したら」と言われたこともあった。「偉大な画家になるように育てるのが大学じゃないですか。わたしはやめませんって言ったんです」と笑う。結婚し、子を生み、大学に残った一番最初の女性がぬいさんだった。
ぬいさんのアトリエは台所と続いている。「女の絵かきは台所でジャガイモを煮ながら、絵を描けなくてはだめ。アトリエにこもって、精神修養してイザ描くなんてぜいたくはできません。パンやコーヒーのにおいと油絵の具のにおいが入り交じった生活。そうやって何十年と描いてきました」
ぬいさんは小柄な女性だ。きしゃな体で八㍍ものダイナミックな作品を描く。大胆な構図と繊細な色遣いがパリでも好評だった。はがき大の作品群「青の断章」は「日本の俳句のよう」と評された。小さな作品に込められた感性と端的な表現力が俳句をほうふつとさせたのだろう。
弘前での個展のあとは十月が六本木、十二月に大阪と個展が控えている。「寝る暇がないくらい忙しい。背中をキリでつつかれているような気分でいつも描いています。わたしにとって東京は戦いの場。故郷での個展はやすらぎです」と話すぬいさん。モダンでシティ感覚と言われているぬいさんの作品だが、絵の中の青色は津軽の青空のようにも見えた。
| |
 |
|
|
|
|